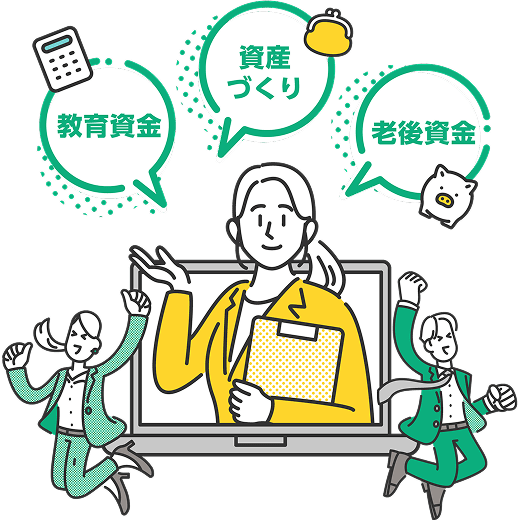「貯金」と「貯蓄」という言葉は似ていますが、実は意味が異なります。家計管理や資産形成を考える上で、この違いを正しく理解することは重要です。本記事では、貯金と貯蓄の定義や役割の違いをわかりやすく解説し、それぞれを上手に活用する方法を紹介します。貯金だけではなく、貯蓄という視点を持つことで、より効果的なお金の管理ができるようになります。
将来のために今から正しいお金の知識を身につけ、資産形成を始めてみませんか?
「何から始めればいいの?」「自分に合った方法は?」 といった悩みも、専門家のサポートで安心して解決できます。ライフプランに合わせた最適な方法を、お金のプロに無料相談をして一緒に考えてみませんか?将来の不安を一歩ずつ解消し、安心してお金の管理ができるようお手伝いします。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
貯金と貯蓄の違いとは?
「貯金」と「貯蓄」、この2つの言葉をあまり区別せずに使っている人は多いのではないでしょうか。まずは2つの言葉の違いを見てみましょう。
この目次でわかること
- 「貯金」は預貯金のこと
- 「貯蓄」は総合的な資産
「貯金」は預貯金のこと
そもそも 「貯金」とは郵便局にお金を預けること です。それに対して、 銀行や信用金庫などの金融機関にお金を預けることを「預金」 と言います。これらを「預貯金」と言いますが、日常的には「貯金」と「預金」は区別されずに、あわせて「貯金」と呼ばれています。
特徴としては、元本保証の安全商品なこと、普通預貯金であれば、すぐに引き出せて、生活費に使ったり、万一の時の予備資金として活用できます。
「貯蓄」は総合的な資産
「貯蓄」は貯金に加えて、投資商品、貯蓄性保険などを含む総合的な資産 を指します。学資保険、個人年金、養老保険といった貯蓄性保険で、すぐには引き出せない資産も貯蓄に含まれます。
元本保証の安全商品である預貯金、貯蓄性保険に加え、株式、投資信託、債券、その他投資商品も貯蓄に含まれます。貯蓄は金融商品全般を指すと考えるとわかりやすいでしょう。
貯金と貯蓄をどう使い分ける?
厳密にいえば貯金は貯蓄に含まれますが、あえて2つを別のものとして考えて、使い分けを考えてみましょう。
この目次でわかること
- 目的別に管理することが重要
- 家計管理における貯蓄率の目安
目的別に管理することが重要
基本的には 短期的な支出に備えるのが貯金で、将来の資産形成のために蓄えるのが貯蓄 だと考えましょう。
まずは、日々の生活費の赤字補てん、入院や冠婚葬祭など急な出費に備えるお金が必要ですが、これは、元本保証ですぐに引き出せる貯金に預けます。3年など近々に使う予定の住宅購入の頭金や車の買い替え費、旅行費なども貯金を利用するのが賢明です。
しかし、貯金は利率が決まっている分、大きく増える可能性はありません。ですから、将来に向けて貯めるお金は投資商品を利用するのが一考です。
つまり、 小さい子どもの将来の学費、老後費用などは貯蓄で準備する と考えるといいわけです。
家計管理における貯蓄率の目安
家計管理をするには、まず一カ月の支出を把握します。そして、 収入の20〜30%を貯蓄に回せたら理想的 です。
貯蓄のなかで、まずは生活防衛資金として、3〜6か月分の生活費を貯金しましょう。この貯金をクリアすることができたら、そのあとは貯金を増やしていくのではなく、投資などの資産運用を考えることがオススメです。
貯金だけでは不十分?インフレ対策も考えよう
貯金だけではなく投資も考えなくてはいけないのはなぜか考えてみましょう。
この目次でわかること
- インフレによる資産価値の目減り
- そもそもインフレって悪いこと?
- 貯金がインフレに弱い理由
- 貯蓄の中に「投資」を組み込む
インフレによる資産価値の目減り
貯蓄のなかの割合が貯金100%だと、どういった不都合が生じるのでしょうか。
今の経済の流れは「インフレ」に向かっています。「インフレ」とは「インフレショーン」のことで、物価が持続的に上昇することです。
みなさんも物価上昇は肌で感じていると思いますが、去年は100円で買えたものが、今年は120円だったりします。これはつまり、お金の価値が目減りしているということ。
現在の物価上昇が約3%とすると、貯金の利率は0.25%といったところなので、預けていても、お金の価値は目減りしてしまっていることになります。
それに対して、投資の期待リターンは積立投資を長く続けると4%と言われていますので、ここで運用すればお金の価値は目減りしないということなのです。
そもそもインフレって悪いこと?
さて、インフレとは悪いことなのでしょうか?必ずしも、そうとはいえません。
インフレとは物価が一定範囲で上昇している状態 です。価格が上がるのは、それだけ欲しい人が多い(需要が多い)ということです。価格が上がれば、企業はそれだけ利益を出していけて、結果的に、そこで勤める社員の給料も上がっていきます。つまり、経済成長をしていくことで、お金がどんどん回っていくということなのです。
日本はこれまでの30年間は賃金の水準がほとんど上がっていませんでした。つまり、日本は今までインフレも起こらないが賃金も上がらないという状態でした。国外に目を向けてみますと、日本のこの状態のほうが例外的です。
そのこともあって、日本のインフレも一時的な状態ではなく、大きな流れとしては今後も続くと予想されています。
貯金がインフレに弱い理由
貯金はインフレに強い金融商品でないことは、先ほど説明したとおりです。
お金の価値が相対的に下がるインフレが進めば、貯金は使わなかったとしても資産が目減りしていく といえます。そのため、貯蓄の中に貯金以外の選択肢を持つことの重要性が増してきているのです。
貯蓄の中に「投資」を組み込む
インフレリスクに備えるために有効な手段のひとつが「投資」です。
投資は元本割れする可能性があるので怖いと考える人もいるでしょう。そんな人にオススメなのが、「長期・積立・分散」で投資をすることです。この戦略で投資をすれば、短期的な値動きやひとつの投資対象の値動きに影響を受けすぎないので、元本割れのリスクが低くなるのです。
先ほど書いた投資の期待リターンは4%という数字も、スタンダードな国際分散投資を20年間続けた場合に、もっとも期待できる運用収益は4~6%だというデータが根拠となっています。
NISAやiDeCoは「長期・積立・分散」に適した投資商品が多く、これまで投資をやったことがない投資初心者向きの制度になっています。運用益非課税などの税制優遇も受けられるので、まずはNISAやiDeCoを利用するところから始めてはどうでしょうか。
NISAについて詳しく知りたい方は『 新NISAとは?初心者にもわかりやすく仕組みを解説! 』も併せて読んでみてください。
まとめ
「貯金」と「貯蓄」は似た言葉ですが、意味や役割が異なります。貯金は日常的な資金管理、貯蓄は長期的な資産形成に活用されます。適切なバランスを取ることで、安心して将来に備えることができます。貯金だけではインフレに対するリスクがあるため、投資などの資産運用を視野に入れた貯蓄の考え方を持つことが重要です。
将来のために今から正しいお金の知識を身につけ、資産形成を始めてみませんか?
「何から始めればいいの?」「自分に合った方法は?」 といった悩みも、専門家のサポートで安心して解決できます。ライフプランに合わせた最適な方法を、お金のプロに無料相談をして一緒に考えてみませんか?将来の不安を一歩ずつ解消し、安心してお金の管理ができるようお手伝いします。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。