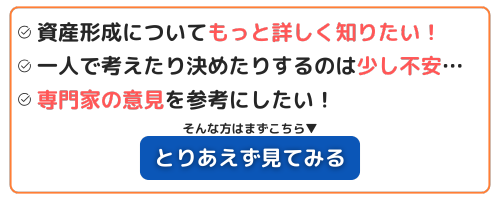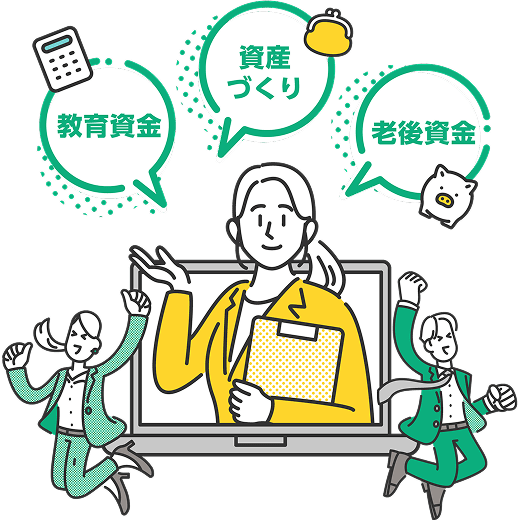「NISAは何歳から利用できるのか?」という疑問を持つ方は多いでしょう。2024年から始まった新しいNISA制度や、ジュニアNISAの終了など、制度が大きく変化しています。本記事では、新NISAが利用できる年齢制限、ジュニアNISAの概要について詳しく解説します。さらに、若い頃から資産形成を始める重要性も具体例を交えてご紹介します。
将来のために今から正しいお金の知識を身につけ、資産形成を始めてみませんか?
資産形成の方法を知ることで、選択肢の幅が広がります。 専門家による無料相談で、あなたのライフプランに沿った資産形成のヒントを見つけてみませんか?プロの無料相談を活用し賢く資産を増やすチャンスを握れます。お気軽に無料相談をご利用ください。
NISAは何歳から利用できる?基本情報
2024年から新NISAが始まりました。制度が変わり使いやすくなったことが特徴です。満18歳から利用することができます。
この目次でわかること
- 新NISAの年齢制限
新NISAの年齢制限
新NISAは 日本国内に住民票がある「満18歳以上」の人が利用可能 です。
旧NISAでは制度を利用できる期間に制限がありましたが、新NISAではこの制限が撤廃され、非課税保有期間は無期限になりました。また、非課税で運用できる年間投資額も大きく引き上げられました。
ほとんどすべての面で、以前よりもメリットが大きくなっていますが、 「ジュニアNISA」の代わりの制度は作られませんでした。つまり、未成年がNISAを利用することはできなくなりました。
ジュニアNISAの概要と2024年以降の運用方法
ジュニアNISAとはそもそもなにか、ジュニアNISAで運用した資産は今後どうなるのかを解説します。
この目次でわかること
- ジュニアNISAの基本
- 2024年以降の変更点
ジュニアNISAの基本
「ジュニアNISA」は子ども名義の口座で0歳から17歳まで、年80万円まで非課税で投資ができる制度でした。
2023年で新規申込は終了しています。 つまり、現時点でジュニアNISAに投資したことがないという人は、なにも気にする必要はありません。
一方で、ジュニアNISAに投資しているという人は、その資産をこの先どのように運用していくべきか気にしておく必要があります。
2024年以降の変更点
ジュニアNISAは制度の廃止が決定され、 2025年現在、ジュニアNISAの口座を持っている人も新規購入はできなくなっています。
ジュニアNISAは18歳までは払い出しができないという制限がありましたが、制度廃止にともなって、現在は18歳未満でも非課税で払い出すことができます。
引き出す場合は一部ではなく、全額を払い出してジュニアNISAの口座を閉鎖する必要があります。 保有するだけなら、2025年以降も18歳になるまでは非課税で保有し続けることができます。
注意しなくてはいけない点は、 ジュニアNISAの資産をそのまま、本人名義の新NISAの口座に移管することはできない ということです。
18歳になると、課税口座に移管されることになります。つまり、ジュニアNISAを利用していた場合は、 18歳になる前にタイミングをみて、非課税のメリットを使えるうちに売却して運用を終了させた方が良さそう です。
NISAは18歳から利用できる
新NISAは18歳から利用できることを確認しました。それでは次に、若い世代がNISAを利用して資産運用することのメリットを見ていきましょう。
この目次でわかること
- 若い世代がNISAを利用するメリット
- 長期投資のメリット
- 少額から始められる手軽さ
- 金融リテラシーの向上
- 親子で考える資産形成
若い世代がNISAを利用するメリット
若い頃からNISAを始めることの大きなメリットは、資産を運用する期間を長く取れることです。
NISAは制度の設計上、短期的な売買には向いていません。NISAの年間投資上限額はつみたて投資枠が120万円、成長投資枠が240万円ですが、上限額まで投資した場合、売却したとしても次の年まではもう投資ができません。
また、用意されている商品も中長期的な投資に向いている商品が多いです。つまり、 NISAを利用するなら長期的な視点で投資することが最適 です。
長期投資のメリット
短期的な値上がりを予想して、まとまったお金を一括で投資することはリスクが高く、初心者にはオススメしません。 このリスクを減らすためにオススメなのは、長期的に積立で投資を続けていくことです。
相場というのは、短期的には上がり下がりがあるものですが、長期的に積立で投資をすることで、相場の変動によるリスクを抑えられます。
また、投資期間が長いほど、得た利益を元本に組み込み、どんどん元本が大きくなっていく 「複利効果」を得ることができます。この「複利効果」の恩恵を受けられることが、長期投資の大きなメリット です。
少額から始められる手軽さ
新NISAにはつみたて投資枠と成長投資枠があり、 はじめて利用する場合には、まずはつみたて投資枠から利用することをオススメ します。
つみたて投資枠では、投資信託を購入するときの手数料はどの金融機関でも無料です。
また、ネット証券では月100円から、銀行では月1000円から最低積立額を選ぶことができます。月数千円なら大学生でも始めやすく、この手軽さも新NISAの魅力です。
金融リテラシーの向上
投資経験を通じて、 資産運用や経済について学べるというメリット があります。
いくら「NISAは放ったらかしでOK」と言われても、全くなにも考えずに投資を始めるほうが逆に難しいものです。
長期投資をする場合、相場の上がり下がりに一喜一憂するのは良くありませんが、実際に自分のお金を投資していれば、相場がまったく気にならないという人の方が少数派です。相場が下がれば、なぜ下がったのかが知りたくなるもの。こういったきっかけからも経済について知っていくきっかけができます。
また、投資信託を選ぶ際も、株式だけでも全世界株式(通称オルカン)、米国株式、国内株式、先進国株式、新興国株式などなど、投資対象はいろいろとあります。
こういったことを比較して見てみるだけでも、世界経済について興味を持つことができるようになります。
親子で考える資産形成
ジュニアNISAでは0歳から始められたのに対して、新NISAでは18歳からになりました。
18歳よりも若い年齢から、子どもを投資に触れさせて金融リテラシーの教育をしたい場合、通常の課税口座で資産運用を行うことになるので、非課税の優遇は受けられないということになります。
「金融リテラシー」をつけることを目的とする場合、 幼い子どもにとって、資産形成はリアリティのない話になってしまうことが多い です。お金の価値がわかってくる大学生くらいの年代になってからの方が、資産形成や経済のことについて伝わりやすいことも確かです。
また、親の立場としても、子どもと資産形成について話すとなれば、20年や30年という期間ではなく、50年や60年といった期間で考える必要が出てきます。
NISAをきっかけに、 長期的な目線で親子で考えてみると、また違った側面で経済をとらえることができます。
18歳からのつみたてNISA運用シミュレーション
18歳からNISAのつみたて投資枠を使って資産運用した場合をシミュレーションしてみましょう。
この目次でわかること
- 20年間積み立てた場合の資産成長
- 収入に応じた積立額の調整
- リスクを理解する
20年間積み立てた場合の資産成長
金融庁の「つみたてシミュレーター」 を使って、平均利回り3%で毎月1万円を積み立てた場合に20年後にはどうなっているかをシミュレーションすると次のようになります。
月1万円の積み立てなら年12万円ですから、元本は20年で240万円になります。平均利回りが3%だった場合、運用収益だけで88万円になり、合計で328万円になります。
月3万円の積み立てなら20年で元本は720万円、運用収益は265万円になり、合計で985万円になります。この運用収益の差からも複利の効果が大きいとわかります。
収入に応じた積立額の調整
上のグラフは月1万円を積み立てた場合ですが、 社会人になって収入があがれば積立額を増やしていくこともできる でしょう。
月1万円で継続しながら、ボーナスが出た月は多めに10万円積み立てるなどの設定をすることもできますし、大きな出費がある年なので今年は積み立てをしないということもできます。
無理のない範囲で積み立てを続けていくことが重要です。
リスクを理解する
「無理のない範囲で」と書きましたが、たとえば 貯金をまったくせずに余裕資金をすべてNISAに回すのはオススメできません。
NISAはいつでも引き出して現金化できることが魅力ですが、その使い勝手の良さから、「貯金はせずにお金は全部NISAに回そう」なんていう極端な意見が出ることもあります。
ですが、NISAは投資なので、リスクは0にはなりません。元本保証がないので、相場が急落すれば、元本割れすることもあります。このときに、資産をすべてNISAで運用していると、生活が立ち行かなくなってしまうなんてことになりかねません。
また、先述したようにNISAは長期運用に最適な制度です。せっかくNISAを利用していても、すぐに引き出して使ってしまっていると、複利の効果が得られずに、制度は利用したけれど、結局ぜんぜん資産は形成されませんでした。ということになる可能性もあります。 制度の特徴を理解して賢くNISAを活用しましょう。
まとめ
NISAは18歳から利用可能で、若い頃から資産形成を始めることで複利効果を最大限活かすことができます。この記事を参考に、NISAの利用年齢や制度の特徴を理解し、最適な資産運用を始めてみてください。
将来のために今から正しいお金の知識を身につけ、資産形成を始めてみませんか?
資産形成の方法を知ることで、選択肢の幅が広がります。 専門家による無料相談で、あなたのライフプランに沿った資産形成のヒントを見つけてみませんか?プロの無料相談を活用し賢く資産を増やすチャンスを握れます。お気軽に無料相談をご利用ください。