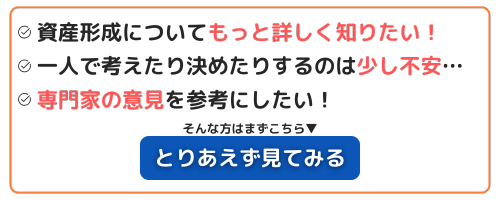2024年から新NISAがスタートし、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つを組み合わせて利用できるようになりました。しかし、それぞれの枠にどんな違いがあり、どちらを選ぶべきか迷う方も多いはずです。本記事では、両者の違いを具体的に解説します。
将来のために今から正しいお金の知識を身につけ、資産形成を始めてみませんか?
資産形成の方法を知ることで、選択肢の幅が広がります。 専門家による無料相談で、あなたのライフプランに沿った資産形成のヒントを見つけてみませんか?プロの無料相談を活用し賢く資産を増やすチャンスを握れます。お気軽に無料相談をご利用ください。
新NISAとは?制度改定の背景と概要
2024年1月からスタートした新NISAの最大のポイントは、つみたて投資枠と成長投資枠の2口座があり、両方の併用が可能となったことです。なぜ併用が可能になったのでしょうか。その理由を紐解きます。
この目次でわかること
- 2024年からの新制度
- なぜ制度が変わったの?
2024年からの新制度
これまでのNISAでは、年間投資枠や投資対象の異なる「一般NISA」と「つみたてNISA」の2つの枠組みがあり、どちらか一方を選ぶ必要がありました。 2024年にスタートした新NISAでは、この2つの枠組みが統合され、併用が可能 となりました。
また、制度の恒久化や年間投資枠の引き上げなどが行われ、誰にとっても利用しやすい制度へと進化をしています。
なぜ制度が変わったの?
NISA制度は、 国民の資産形成を後押しするために誕生した制度 です。2014年に「一般NISA」、2018年に「つみたてNISA」がスタートしました。
ただ、この2つの制度は同一年度内にはどちらか一方しか選択ができず、使いにくさがありました。その不便さを解消するため、2024年にどちらも併用でき、投資額も拡大した新制度へと生まれ変わったのです。
つみたて投資枠と成長投資枠の違い
併用できるようになった、つみたて投資枠と成長投資枠。それぞれの違いを確認しましょう。
この目次でわかること
- 年間投資枠の違い
- 生涯投資枠の違い
- 運用可能な金融商品の違い
年間投資枠の違い
つみたて投資枠と成長投資枠では、年間投資枠が異なります。 つみたて投資枠は年間120万円、成長投資枠は年間240万円、で合計360万円を投資できます。この年間投資枠は、1月〜12月の1年間で管理され、その年で使いきれなかった枠を持ち越すことはできません。 例えば、その年のつみたて投資枠が10万円残っていても、翌年の枠が130万円に増えるわけではありません。

生涯投資枠の違い
新NISAでは、年間投資枠のほかに、1人あたり1800万円の生涯投資枠も設けられています。 この範囲内であれば、自由に売買が可能です。 ただし、成長投資枠のみ利用の場合は生涯投資枠は1200万円へと下がります。
つまり、成長投資枠で1200万円を投資しているなら、つみたて投資枠で600万円まで投資が可能ですし、成長投資枠で100万円しか投資していないなら、つみたて投資枠で1700万円まで投資することができるということです。
仮に、生涯投資枠が上限まで達したとしても保有商品の一部を売却すれば、翌年には空いた分に再び投資できるようになります。 保有商品の購入金額の合計が生涯投資枠の上限を超えない限り、何年間でも保有や新規投資を続けることができるのです。

運用可能な金融商品の違い
投資できる対象商品も異なります。 つみたて投資枠で購入できるのは、金融庁が認めた長期・積立・分散投資に適した投資信託のみ。 厳選された 約280の投資信託が対象 です。
一方の成長投資枠で購入できるのは、約2000の投資信託のほか、国内外の株式、J-REIT(不動産投資信託)、ETF(上場株式投資信託)など 。つみたて投資枠では購入できない幅広い商品への投資が可能です。

「つみたて投資枠」と「成長投資枠」のメリット・デメリット
2つの枠が併用できるようになった新NISA。それぞれのメリットとデメリットを確認しましょう。
この目次でわかること
- つみたて投資枠のメリット
- つみたて投資枠のデメリット
- 成長投資枠のメリット
- 成長投資枠のデメリット
つみたて投資枠のメリット
つみたて投資枠のメリットは、投資初心者でも失敗しにくい制度設計になっている点です。元本割れのリスクを軽減しつつ、安定的な資産形成を行うためには、長期の積立・分散投資が有効です。
つみたて投資枠では、この「長期・積立・分散」投資に適した投資信託のみが揃っています。 投資スタイルも、定期的に一定額で購入を続ける積立投資しか認められていません。 金融機関によっては月100円程度からの積立も可能なので、少額から始めやすいという特徴もあります。
つみたて投資枠のデメリット
つみたて投資枠のデメリットは、自分の運用したい商品がない可能性がある という点です。先述の通り、つみたて投資枠で購入できるのは、金融庁が定めた基準をクリアした約280の投資信託のみ。大部分がインデックス型の投信です。
インデックス型の投信は、市場と同等の値動きをするため、長期的に積み立てていくことで市場の成長に伴って利益を得られる可能性があります。インデックス型の投信が大部分であるつみたて投資枠の制度上、 短期的なリターンは狙いにくくなっています。

成長投資枠のメリット
成長投資枠のメリットは、幅広い商品を活用できる点 です。対象商品は、約2000の投信に加え、国内外の株式、J-REIT、ETFなど。今後値上がりが期待できる株式銘柄への一括投資が可能で、積極的な運用を行うことができます。
また、 つみたて投資枠で購入できる投信も全て対象 です。つみたて投資枠では足りないという人は、その延長で成長投資枠の中で投信積立を行うといったリスクを抑えた運用も可能です。
成長投資枠のデメリット
成長投資枠では、一括投資も積立投資も可能なので「つみたて投資枠の拡張版」ともいえます。そのため、あまりデメリットはないのですが、強いてあげるとすれば、 リスクの高い商品に投資する場合には短期的な値動きに左右されやすく、大きな損失を生む可能性がある ということでしょう。
NISAは運用による値上がり益は非課税なのが特徴。NISA口座で保有商品が塩漬けになってしまうとNISAのメリットを生かせないことになります。

NISAの活用術
積立投資枠と成長投資枠は併用することで、さまざまな運用を行うことができます。活用のポイントをお伝えします。
この目次でわかること
- つみたて投資枠の活用方法
- 成長投資枠の活用方法
つみたて投資枠の活用方法
NISAを上手に使いこなしたいなら、 まずはつみたて投資枠の利用を検討しましょう。 毎月一定額を積み立てることで、リスクを抑えた運用が可能です。公的年金の縮小、インフレなど、先の読めない現代において、投資で「お金に働いてもらう」のは必須のリスクコントロール術です。
毎月のお給料から無理のない金額を積み立てていき、10年、20年、それ以上の長いスパンで運用しましょう。
成長投資枠の活用方法
成長投資枠には、さまざまな活用方法があります。
まずは、つみたて投資枠の延長で成長投資を行う方法です。 つみたて投資枠は年間120万円なので、月10万円ずつの積み立てが限度 。それ以上積み立てたいのであれば、成長投資枠で積立投資を上乗せしましょう。
次に、 一括投資については国内外の個別株式銘柄やJ-REIT、ETFへの投資が可能 です。積立投資よりもリスクは高まる傾向があるので、あくまで趣味として余剰資金で行うことが大切です。
余剰資金の範囲内であれば、お気に入りの銘柄に投資して株主優待を楽しんだり、積極的にリターンを狙うアクティブ型の投信に投資してみたり、投資の楽しさを味わうことができます。
結論:新NISAで賢く資産形成を始めよう
制度が拡充された新NISAでは、新社会人、子育て世代、定年退職世代、どのライフステージにいる人でも活用しやすくなっています。まだNISAを始めるか迷っている人は、ぜひ少しでも早く始めて、運用期間を長く確保しましょう。
この目次でわかること
- つみたて投資枠と成長投資枠を上手に使い分ける
- まずは少額からスタート
つみたて投資枠と成長投資枠を上手に使い分ける
積立投資でコツコツと資産形成できるつみたて投資枠と、あらゆる投資スタイルで柔軟に活用できる成長投資枠。 まずは、両者の特徴を理解することがNISAを使いこなす第一歩です。 その上で、自分に合った活用方法を見つけましょう。
まずは少額からスタート
これからNISAを始める人は、まずは少額からつみたて投資枠で積立投資をスタートしましょう。投資に慣れてきたり、資金に余裕が出てきたりしたタイミングで、積立金額の増額を検討するといいでしょう。
NISAを上手に活用するポイントは、つみたて投資枠でのコツコツ運用を継続することです。途中でまとまった資金ができたら成長投資枠で投信積立以外の投資にも挑戦するという活用がおすすめです。
まとめ
新NISA制度の導入によって、さまざまな商品や運用スタイルで資産運用をできるようになりました。つみたて投資枠と成長投資枠の違いをしっかり理解し、自分に合った投資スタイルを見極めることが重要です。まずは今の自分に無理のない範囲で始め、将来の資産形成を着実に進めていきましょう。
将来のために今から正しいお金の知識を身につけ、資産形成を始めてみませんか?
資産形成の方法を知ることで、選択肢の幅が広がります。 専門家による無料相談で、あなたのライフプランに沿った資産形成のヒントを見つけてみませんか?プロの無料相談を活用し賢く資産を増やすチャンスを握れます。お気軽に無料相談をご利用ください。