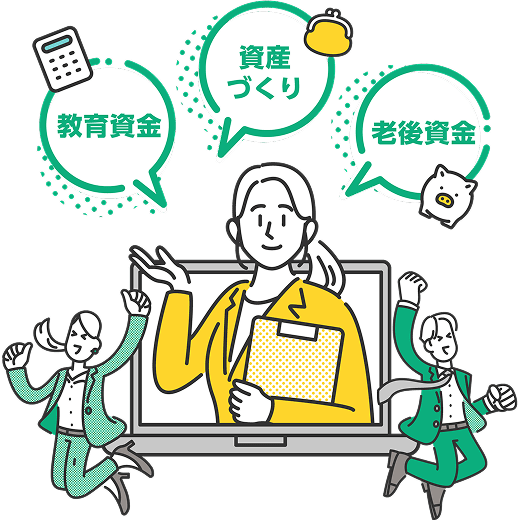iDeCo(個人型確定拠出年金)は、老後資産形成に役立つ制度ですが、掛け金には上限があり、働き方によって異なります。自分の働き方ではいくらまで拠出できるのか、上限を超えた場合どうなるのか、掛け金を増やすべきかどうか悩む人も多いでしょう。本記事では、iDeCoの掛け金上限を職業別にわかりやすく整理し、変更方法や最適な拠出額の決め方について詳しく解説します。さらに、NISAなど他の制度との組み合わせ方についても紹介し、効率的な資産運用のヒントをお伝えします。
将来のために今から正しいお金の知識を身につけ、資産形成を始めてみませんか?
資産形成には、情報収集と正しい知識が必要不可欠 です。今から始められる資産運用方法を専門家が無料でご提案します。一歩踏み出すことで、将来の不安を少しずつ減らすことができます。まずは無料相談で、あなたの資産形成プランを一緒に考えてみませんか?
iDeCoの掛け金上限は働き方・年金加入状況によって異なる
iDeCoの掛け金の上限は公的年金や企業年金の加入状況によって変わります。
この目次でわかること
- 働き方別の掛け金上限一覧
働き方別の掛け金上限一覧
どういった公的年金に加入しているかは、 働き方によって第1号被保険者~第3号被保険者に分かれています。iDeCoの年間掛金は、この分類によって掛金上限額が変わります。
iDeCoは老後資産形成のための制度なので、老後の年金受給額にある程度対応するように掛け金上限額を設定しています。まずは、働き方によるiDeCoの掛け金の上限の違いを図で確認しましょう。
*月額の上限は、5万5000円-(厚生年金基金の掛金+確定給付企業年金(DB)の掛金+確定拠出年金制度(DC)の掛金)
企業年金が充足していると、月額の上限額が2万円以下になることや、iDeCoに加入できないこともある
働き方ごとの掛け金の上限額の違いを解説
働き方によって掛け金の上限額がそれぞれ設定されているのはなぜか解説します。
この目次でわかること
- 自営業者が最も高い上限額を設定できる理由
- 企業年金のある会社員・公務員の上限額が低い理由
自営業者が最も高い上限額を設定できる理由
自営業者・個人事業主、フリーランスといわれるような働き方の人は月6万8000円まで上限額が設定されていて、他の働き方よりも大幅に高い です。これはiDeCoが老後資産形成のための制度だからです。
第1号被保険者である自営業者等は、国民年金にのみ加入しています。国民年金と厚生年金の2つに加入している会社員・公務員に比べて、自営業者等は老後の公的年金の支給は少なくなります。
そのぶんをフォローするために、自営業者等のiDeCoの掛け金の上限額は高く設定されているのです。
厚生年金に加入できないぶん、自分で自分の年金を積み立てていくことが推奨されているというイメージ です。
企業年金のある会社員・公務員の上限額が低い理由
第2号被保険者である会社員・公務員の中でも、 会社に企業年金のある会社員と公務員はiDeCoの上限額が低く設定 されています。
これは先ほどの自営業者等の掛け金の上限額が高く設定されている理由の逆だとイメージするとわかりやすいです。
企業年金がある会社員や公務員は老後の年金が手厚いので、iDeCoの掛け金の上限額も低く設定されている のです。
掛け金の上限を超えた場合どうなる?
掛け金に上限が設定されていると、「上限を超えてしまった場合どうなるの?」という疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。
この目次でわかること
- 掛け金の上限を超えないように注意
- 働き方に変更があった場合の影響
掛け金の上限を超えないように注意
iDeCoは上限額以上に拠出することはできません。
iDeCoの掛け金の上限額は、 自営業者等の場合は「国民年金基金」「国民年金付加保険料」の拠出額との合計が上限額 になり、 会社員の場合は企業年金「DC」「DB」などの拠出額との合計が上限額 になります。
たとえば、会社員で企業年金が充実していた場合、iDeCoの月額の上限額が2万円以下になったり、そもそもiDeCoには加入できないということもあります。
働き方に変更があった場合の影響
転職や退職を機に働き方が変わり、iDeCoの上限額も変わるというケースがあります。 このときには、手続きが必要なので注意しましょう。
たとえば、企業型DCのある会社から、企業型DCがない会社に転職した場合、 資産をiDeCoに移管する手続きをする必要があります。 移管申込書に必要事項を記入して、金融機関に移管を申し込みます。移管時に運用商品はすべて売却されて現金化され、その後新たな商品で運用することになります。
企業型DCの加入資格喪失後6カ月以内に、この移管手続きを行わなかった場合、資産は国民年金基金連合会へ自動移管されます。移管後は資産の運用はされず、手数料も引かれ続けます。 こうなってしまうと明確にデメリットをこうむるので、転職や離職の際には注意が必要です。
iDeCoの掛け金は変更できる?手続き方法を解説
iDeCoを続けていくなかで掛け金を増額したい・減額したいと思った場合、年1回までは掛け金を変更することができます。
この目次でわかること
iDeCoの掛け金の基本的な仕組み
加入・掛け金変更の手続き方法
iDeCoの掛け金の基本的な仕組み
iDeCoの積み立ては毎月同額である必要はありません。
本記事ではここまで、上限額は月額ベースで書いてきましたが、 制度上は年額の上限額を超えなければ問題ありません。
毎月5000円を拠出し、ボーナスが支給される月は10万円を拠出するという積み立ての仕方も選ぶことができます。また、年に一度だけ一括で拠出するという方法も選べます。
iDeCoは12月には必ず引き落としをするというルールがあるので、年に一度の拠出を選んだ場合、12月26日を引き落とし日に設定する必要があります。 また、毎月の拠出額の最低額が5000円なので、 年に一度の拠出の場合、12カ月分の6万円以上を拠出額に設定する必要があります。
加入・掛け金変更の手続き方法
iDeCo初加入の場合、 加入申込書を提出した月の翌々月から拠出が始まります。 たとえば、4月に申込書を提出した場合、引き落としは6月からになるので、拠出額は6月以降に記入します。
また、掛け金変更の場合、金融機関によっては、変更が反映されるのは変更届を出した翌年からになることもあります。
iDeCoの掛け金は上限まで拠出すべき?
iDeCoの掛け金を上限まで拠出する場合のメリットと、上限まで拠出しないほうが良いケースを見てみましょう。
この目次でわかること
- 上限まで拠出するメリット
- 無理に上限まで拠出しない方がよいケース
上限まで拠出するメリット
上限まで拠出すれば、そのぶん元本が大きくなります。非課税の運用益も元本に組み入れられるので、投資の複利の効果を得ることができます。
これに加えて、iDeCoには税制優遇による節税効果があります。iDeCoを最大限活用した場合、その節税効果はどれほどになるのか、iDeCo公式サイトでシミュレーションすると次のようになります。
 出典:
iDeCo公式サイト「かんたん税制優遇シミュレーション」
出典:
iDeCo公式サイト「かんたん税制優遇シミュレーション」
30歳から65歳までの35年間で、自営業者の上限月額6万8000円を積み立てた場合の節税額は約500万円、企業年金のない会社員の上限月額2万3000円を積み立てた場合の節税額は約193万円です。
節税額だけでもかなりの金額だということがわかります。
無理に上限まで拠出しない方がよいケース
iDeCoを無理に上限まで拠出しない方がよいケースもあります。 生活資金の余裕がない場合や、普通預金などのすぐに引き出せる貯蓄がほとんどない場合 です。iDeCoは原則60歳まで引き出せず、この縛りはかなり厳しいです。
人生、どこかのタイミングでは60歳より前にまとまったお金が必要になることもあるでしょうから、「貯金はないけれどiDeCoをやっているから大丈夫」とは言えません。
まずは生活の基盤が安定してからiDeCoを始めることがオススメです。
iDeCoとNISAを併用するメリット
iDeCoもNISAも運用益非課税という大きなメリットがあるので、併用できるならば併用したいところです。まずは2つの違いを確認しましょう。
この目次でわかること
- iDeCoとNISAの違い
- どちらを優先すべきか?
iDeCoとNISAの違い
iDeCoのメリットは「所得控除+運用益非課税+受取時の税制優遇」です。 iDeCoの最大のメリットは掛け金が所得控除になり、所得税と住民税が軽減されることです。 つまり、節税効果はNISAよりもiDeCoのほうが高いです。
NISAのメリットは「運用益非課税+自由に引き出せる」こと です。iDeCoが60歳まで引き出せないのに対して、NISAはいつでも引き出し可能な点が人気を集めています。
どちらを優先すべきか?
2つの違いを理解すると、iDeCoとNISA、どちらを優先すべきか?という疑問が出てきます。
まずは NISAを活用し、余裕があればiDeCoを増額する戦略 があります。この戦略の メリットはNISAはいつでも引き出し可能で、自由度が高く資産運用ができる ことです。 デメリットとしては、iDeCoの節税効果を最大限受けられないこと です。
先述したように、生活資金に余裕がないのにiDeCoの拠出額を増やすことはオススメできないので、その場合はこの戦略のほうがいいでしょう。
とはいえ、NISAも長期的な投資のほうが向いている資産運用の方法です。NISAで資産運用をしても、すぐに引き出してしまうのは得策ではありません。
iDeCoは60歳まで引き出せないことはデメリットですが、逆にいうと引き出して使ってしまう誘惑がないとも言えます。
生活資金にそれなりに余裕があるが、 毎月の出費が多く、思うように資産形成ができていないという人は、思い切ってiDeCoを上限まで拠出してから、余裕分をNISAに回す という戦略も有効です。
まとめ
iDeCoの掛け金上限額は働き方によって異なります。掛け金は年1回変更できるため、収入や支出の状況に応じて見直すことが重要です。また、iDeCoだけでなくNISAなどの他の制度と併用し、資産形成のバランスを取ることがポイントです。自分にとって最適な拠出額を考え、賢く老後資産を準備しましょう。
将来のために今から正しいお金の知識を身につけ、資産形成を始めてみませんか?
資産形成には、情報収集と正しい知識が必要不可欠 です。今から始められる資産運用方法を専門家が無料でご提案します。一歩踏み出すことで、将来の不安を少しずつ減らすことができます。まずは無料相談で、あなたの資産形成プランを一緒に考えてみませんか?