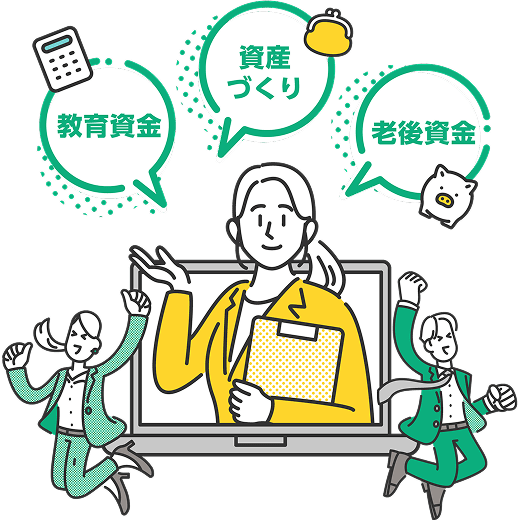iDeCo(個人型確定拠出年金)は老後資産形成のための制度で、最大の魅力は「節税効果」です。しかし、「どのくらい節税できるのか?」「自分の職業・収入ではどの程度のメリットがあるのか?」と疑問に思う方も多いでしょう。本記事では、iDeCoの節税ポイントを整理し、具体的な計算例や職業別のメリットを詳しく解説します。また、NISAとの違いや注意点についても触れ、賢く活用するためのポイントを紹介します。
将来のために今から正しいお金の知識を身につけ、資産形成を始めてみませんか?
資産形成には、情報収集と正しい知識が必要不可欠 です。今から始められる資産運用方法を専門家が無料でご提案します。一歩踏み出すことで、将来の不安を少しずつ減らすことができます。まずは無料相談で、あなたの資産形成プランを一緒に考えてみませんか?
iDeCoの節税効果とは?3つの節税ポイントを解説
iDeCoには税制優遇が用意されていて節税できるポイントが3つあります。まずはこの3つの節税ポイントを見てみましょう。
この目次でわかること
- 掛け金が全額所得控除になる
- 運用益が非課税になる
- 受け取り時に税制優遇がある
掛け金が全額所得控除になる
iDeCoは掛け金が所得控除の対象となり、所得税・住民税が軽減されます。 所得税と住民税は「課税所得」をもとに計算しますが、iDeCoの掛け金は全額を「課税所得」から引くことができます。
つまり、「課税所得」が低くなるので、所得税と住民税が軽減されるのです。掛け金が全額所得控除になる税制優遇はNISAにはなく、iDeCo特有の大きなメリットです。
運用益が非課税になる
通常、投資の運用益には20.315%(約20%)の税金がかかります。この 約20%の税金がiDeCoなら非課税 となります。
運用益が非課税となるのはNISAも同様で、この運用益非課税のメリットが大きいので、NISAとiDeCoは注目を集めました。
iDeCoの場合、60歳まで引き出すことができませんが、そのぶん運用益は投資元本にプラスされて投資し続けることになるので、雪だるま式に元本が増えていく「複利の効果」を得ることができます。
受け取り時に税制優遇がある
iDeCoは60歳~75歳の間で受け取り時期を設定できます。この受け取り方は、一括で受け取る「一時金形式」、分割で受け取る「年金形式」、その2つを組み合わせた形式の3種類から選ぶことができます。
そして、この受け取りの際にも非課税枠が用意されていることがiDeCoの大きなメリットです。 一時金として受け取る場合には「退職所得控除」が、年金として「公的年金等控除」が利用できます。
iDeCoの節税メリットを具体的にシミュレーション
実際のところ、iDeCoを使うとどのくらい節税になるのかが気になるところです。iDeCo公式サイトでシミュレーションがすることができます。具体的な数字を見てみましょう。
この目次でわかること
- 年収別の節税シミュレーション
年収別の節税シミュレーション
年収400万円・600万円・800万円のケースで、それぞれ月額1万円・2万円を掛け金にした場合の年間の節税額は次のようになります。
◆30歳でiDeCoに加入した場合の1年間の節税額
| 年収 | 掛け金 (月額) | 所得税 | 住民税 |
1年間の
節税額の合計 (B-A)+(D-C) |
35年間
積み立てた場合の 節税額の合計 | ||
| iDeCo加入(A) | iDeCo未加入(B) | iDeCo加入(C) | iDeCo未加入(D) | ||||
| 400万円 | 10,000円 | 79,220円 | 85,220円 | 163,440円 | 175,440円 | 18,000円 | 630,000円 |
| 20,000円 | 73,220円 | 85,220円 | 151,440円 | 175,440円 | 36,000円 | 1,260,000円 | |
| 600万円 | 10,000円 | 192,160円 | 204,160円 | 294,660円 | 306,660円 | 24,000円 | 840,000円 |
| 20,000円 | 180,160円 | 204,160円 | 282,660円 | 306,660円 | 48,000円 | 1,680,000円 | |
| 800万円 | 10,000円 | 442,260円 | 466,260円 | 439,880円 | 451,880円 | 36,000円 | 1,260,000円 |
| 20,000円 | 418,260円 | 466,260円 | 427,880円 | 451,880円 | 72,000円 | 2,520,000円 | |
出典: iDeCo公式サイト「かんたん税制優遇シミュレーション」
iDeCoには手数料がかかり、毎月積立をしていれば、年間2,052円がかかりますが、上表でわかるように、 毎月1万円の掛金でも、手数料以上の節税メリットがあることがわかります。 また、同じ掛け金でも収入が高い人のほうが節税額が大きいことがわかります。これは、収入が高い人のほうが税率が高いためです。
職業別のiDeCoの節税効果
iDeCoは働き方によって掛け金の上限額がかわります。上限額を表にすると次のようになります。
この目次でわかること
- 会社員・公務員の場合
- 自営業者・個人事業主の場合
- 専業主婦(主夫)の場合
*月額の上限は、5万5000円-(厚生年金基金の掛金+確定給付企業年金(DB)の掛金+確定拠出年金制度(DC)の掛金)
企業年金が充足していると、月額の上限額が2万円以下になることや、iDeCoに加入できないこともある
会社員・公務員の場合
働いている会社に企業年金がない会社員は月額2万3000円、企業年金がある会社員・公務員は月額2万円が掛け金の月額の上限額 です。
会社員や公務員の場合、住宅ローン控除などはありますが、所得控除ができる制度は少ないです。iDeCoは所得控除を受けながら老後資産を用意できるので、節税したい会社員・公務員にとっては、iDeCoが有力な選択肢となっているのです。
自営業者・個人事業主の場合
自営業者や個人事業主の場合、iDeCoの掛け金の上限は月額6万8000円 です。会社員・公務員よりも大幅に上限額が高いのは、会社員が加入している厚生年金に加入していないぶん、老後の公的年金額が少ないことをフォローするためです。
個人事業主などの場合、「小規模企業共済」に加入する人も多いです。この制度もiDeCoと似た制度で、老後の資産を積み立てつつ、掛け金(月額の上限7万円)は所得控除になるので節税することができます。
また、「小規模企業共済」とiDeCoは併用できるので、どちらも上限額まで利用すると、月13万8000円を積み立てながら所得控除にすることができます。
専業主婦(主夫)の場合
専業主婦(主夫)の場合は配偶者の扶養に入っています。また、パートやアルバイトで働いている人でも、扶養を出ない範囲、いわゆる「年収の壁」を超えないように働いている人もいます。このような働き方の人は年金や社会保険の保険料は自分では負担していません。また、所得税や住民税も納めていません。
ですので、そもそも 節税する税金がないので、iDeCoの節税メリットは活かせません。 ですが、運用益・受け取り時の非課税メリットは活かせるので、老後の資金が国民年金だけでは足りないと思っている場合、iDeCoが老後資産を用意するための選択肢のひとつになります。
iDeCoとNISAの節税効果を比較
iDeCoとNISAの特徴を簡単に比較してみましょう。
この目次でわかること
- iDeCoとNISAの税制メリットの違い
- どちらを優先すべきか?
iDeCoとNISAの税制メリットの違い
iDeCo:所得控除あり・運用益非課税・60歳まで引き出せない(受取時の税優遇あり)
NISA:所得控除なし・運用益非課税・いつでも引き出し可能
iDeCoとNISAを比較した場合、節税という面だけでみれば、所得控除のあるiDeCoのほうが節税効果は大きいです。iDeCoのデメリットは60歳まで引き出せないことです。この点では、いつでも引き出し可能なNISAのほうが自由度が高く、使いやすい制度だといえます。
どちらを優先すべきか?
いつでも引き出し可能という面だけをみると、NISAのほうが使いやすいことは事実なので、iDeCoを利用するメリットはないのでは?と思う方もいるかもしれません。
しかし、ここまでに書いてきたとおり、 節税メリットはiDeCoのほうが大きい です。「iDeCoよりもまずはNISAをやるべき」という意見も多いですが、投資に回せるお金の中から、まずはiDeCoをやって、余ったぶんのお金をNISAに回すという選択も間違いではありません。
iDeCoには注意点が2つある
iDeCoを利用する際には注意したい点が2つあります。60歳まで受け取れない点、受け取る際の税制優遇には上限額がある点です。
この目次でわかること
- iDeCoの注意点① 60歳まで引き出せない
- iDeCoの注意点② 受取時に税金がかかる場合もある
iDeCoの注意点① 60歳まで引き出せない
iDeCoは 原則、60歳まで引き出せません。
たとえば、すぐに引き出せる貯金がほとんどないのに、iDeCoにお金を回していた場合、思わぬアクシデントなどでまとまったお金が必要になっても、それに対応するためのお金が手元にない!という事態になりかねません。
ある程度のまとまったお金は普通預金などで手元にある状態にしてから、iDeCoを始めたほうが安心です。
iDeCoの注意点② 受取時に税金がかかる場合もある
iDeCoは 受取時に税制優遇がありますが、税金がかかる場合もあります。 「退職所得控除」と「公的年金控除」にはそれぞれ上限額が設定されているからです。
たとえば、30年間積み立て、60歳時に一括で受け取る場合、退職金とあわせて1500万円までが非課税になります。65歳から年金形式で受け取る場合、公的年金とあわせて年110万円までが非課税になります。退職金が多い場合や公的年金が多い場合には、税金がかかる場合もあります。
iDeCoの受け取り方は「一時金形式」と「年金形式」を組み合わせることもできるので、非課税メリットを最大限活かすためには、自分にあった受け取り方を考えておくと良いでしょう。
まとめ iDeCoの上手な活用方法
iDeCoは「掛け金が全額所得控除になる」「運用益が非課税」「受け取り時に控除が使える」といった3つの節税メリットがあります。職業や収入によって節税効果の大きさは異なりますが、特に所得が高い人や自営業者には大きなメリットがあります。一方で、「60歳まで引き出せない」という制約があるため、NISAなど他の制度も選択肢に入れて計画的に活用することが重要です。ある程度まとまったお金を普通預金に持ちつつも、貯蓄のなかで貯金の割合が増えすぎないように、iDeCoとNISAを併用していけたら理想的です。自分の状況に合わせて最適な方法を選び、老後資産形成を有利に進めましょう。
将来のために今から正しいお金の知識を身につけ、資産形成を始めてみませんか?
資産形成には、情報収集と正しい知識が必要不可欠 です。今から始められる資産運用方法を専門家が無料でご提案します。一歩踏み出すことで、将来の不安を少しずつ減らすことができます。まずは無料相談で、あなたの資産形成プランを一緒に考えてみませんか?