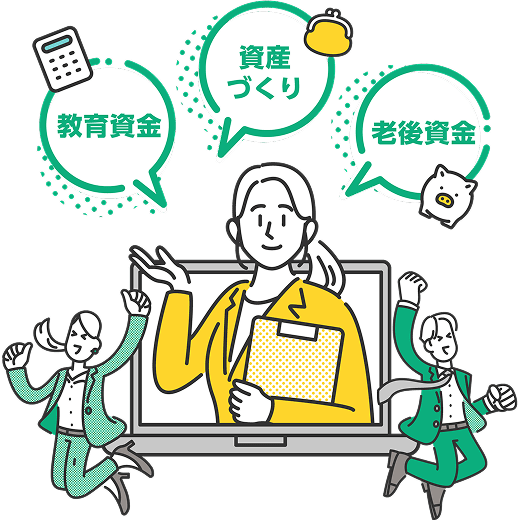iDeCo(個人型確定拠出年金)は老後資産形成のための制度ですが、「デメリットしかない」といったネガティブな意見もよく見かけます。確かに、60歳まで引き出せない、手数料がかかるなどの注意点はありますが、本当にデメリットだけなのでしょうか?本記事では、iDeCoのデメリットとメリットを客観的に解説し、どんな人に向いているのかを詳しく紹介します。NISAや他の投資方法との比較も交えながら、iDeCoの活用を検討する際の判断材料を提供します。
将来のために今から正しいお金の知識を身につけ、資産形成を始めてみませんか?
資産形成には、情報収集と正しい知識が必要不可欠 です。今から始められる資産運用方法を専門家が無料でご提案します。一歩踏み出すことで、将来の不安を少しずつ減らすことができます。まずは無料相談で、あなたの資産形成プランを一緒に考えてみませんか?
iDeCoはデメリットしかない?本当のところを解説
「iDeCoはデメリットしかない」と言われることもあります。なぜそういった意見が出てくるのか、デメリットとメリットの両面を解説していきます。
この目次でわかること
- iDeCoの基本的な仕組み
- 「デメリットしかない」という意見が生まれる理由
iDeCoの基本的な仕組み
まずはiDeCoの基本的な仕組みを説明します。
iDeCoは「個人型確定拠出年金」と言い、 自分の老後資産を自分で積み立てていく制度 です。原則として、20歳~65歳未満までの、国民年金・厚生年金加入者ならば誰でも加入できます。逆にいうと、65歳以上の人や、国民年金を未納、または免除・納付の猶予を受けている人は加入できません。
iDeCoの掛金は下限が月額5000円で、1000円単位で設定できます。上限は働き方によって変わります。詳しくは下図にまとめました。
*月額の上限は、5万5000円-(厚生年金基金の掛金+確定給付企業年金(DB)の掛金+確定拠出年金制度(DC)の掛金)
企業年金が充足していると、月額の上限額が2万円以下になることや、iDeCoに加入できないこともある
iDeCoは老後資産を形成するために作られた制度なので、 厚生年金に加入できない自営業者・フリーランスのほうが掛金の上限が高く設定されています。 第1号、第2号被保険者の上限額は今後引き上げられる見込みです。
「デメリットしかない」という意見が生まれる理由
iDeCoはデメリットしかないと言われる背景には、「60歳まで引き出せないことへの不満」、「口座管理手数料や運用リスクに対する懸念」、「他の投資方法と比べた際の柔軟性の低さ」などの懸念材料があります。
それらのデメリットが税制面での優遇というメリットを上回っていると感じられるために、「デメリットしかない」という極端な意見も出てくるわけですが、実際には 「iDeCoにはデメリットもメリットも両面ある」と言うのが正しい でしょう。
iDeCoの主なデメリットと注意点
iDeCoのデメリットとして挙げられる懸念材料をひとつずつ見ていきましょう。
この目次でわかること
- 60歳まで引き出せない
- 口座管理手数料がかかる
- 運用次第で元本割れのリスクあり
- 掛金の上限がある
60歳まで引き出せない
iDeCoは老後資産を用意するための制度であるため、原則として途中解約はできません。 途中で掛金を積み立てることが難しくなった場合は、掛金の減額や積み立ての停止をすることができますが、好きなタイミングで解約をしてそれまでの積立金+運用益を引き出すということはできません。
これが、普通預金やNISAなどとの最も大きな違いです。iDeCoは老後の資産形成に向けて長期的な資産運用をするための制度なので、短期間での資産形成には向いていないといえます。
口座管理手数料がかかる
iDeCoには手数料がかかります。まず、 口座開設時には2,829円 がかかります。その後、掛金を拠出するたびに(毎月積立をしているなら毎月)、 国民年金基金連合会に月額105円、信託銀行に月額66円、合計171円 がかかります。
これに加えて、金融機関によっては月額数百円の運営管理手数料がかかる場合があります。手数料無料の金融機関もあります。
運用次第で元本割れのリスクあり
iDeCoは運用する商品を自分で選ぶ必要があり、金融機関によって取り扱っている商品は様々です。この商品には大きくわけて2つの種類、「元本保証型」と「投資信託」があります。「元本保証型」は満期まで保有すれば元本+利息分が受け取れます。
「投資信託」は、投資なので元本割れのリスクもあります。そのぶん、「元本保証型」の商品よりもリターンが大きくなる可能性があります。
「元本保証型」と「投資信託」の商品のどちらかを選ばなくてはいけないということはなく、両方を組み合わせて運用することもできます。
掛金の上限がある
iDeCoには掛金に上限があります。先ほども表で説明しましたが、 働き方によって上限額がそれぞれ設定されています。
そのため、iDeCoは高額な資産形成を目指すのには向いていません。iDeCoは投資の側面もありますが、老後資産を安定的に増やすための制度といったイメージのほうが近く、大きく資産を増やしたい人は他の資産運用も利用したほうがいいでしょう。
iDeCoのメリットと活用方法
ここまでiDeCoのデメリットについて書いてきましたが、iDeCoにはもちろんメリットがあります。iDeCoにしかない最大のメリットは、独自の税制優遇を受けられることです。
この目次でわかること
- 所得控除による節税メリット
- 運用益が非課税になる
- 受け取り時の税制優遇
所得控除による節税メリット
税制優遇のひとつめが、掛金が全額所得控除になることです。その分、住民税・所得税の負担が軽くなります。
そもそも税金は、年収から所得控除を引いた額が課税所得になり、この課税所得から税額を計算します。所得控除が増えれば、課税所得が減るので税金の負担も軽くなるわけです。これを節税と言いますが、 会社員には節税のために使える仕組みが少ないので、iDeCoが有力な節税方法となる のです。
普通預金に預けたり、NISAに投資しても原則、こうした節税はできません。ですので、この節税効果がiDeCo特有の大きなメリットといえます。
運用益が非課税になる
投資や預金などの収益には20.315%(約20%)の税金がかかります。銀行預金の利率は微々たるものですが、それにも約20%の税金はしっかりかかっています。この約20%の税金が非課税になるということが、NISAとiDeCoに共通の大きなメリットです。
収益を上げたら、そのぶんを税金が引かれずに受け取ることができるのです。
受け取り時の税制優遇
iDeCoは 60歳~75歳の間で受け取り時期を設定できます。
この受け取り方は、一括で受け取る一時金形式、分割で受け取る年金形式、その二つを組み合わせた形式の3種類から選ぶことができます。そして、この受け取りの際にも非課税枠が用意されていることがiDeCoの大きなメリットです。
一時金として受け取る場合には「退職所得控除」が、年金として受け取る場合には「公的年金等控除」が利用できます。一時金形式の場合、たとえば加入期間が30年の場合、会社からの退職金との合計額に「退職所得控除」が適用され、1,500万円までは全額非課税になります。
iDeCoと他の資産形成方法を比較
iDeCoと他の資産形成方法では、どのような違いがあるのかを比較してみましょう。
この目次でわかること
- iDeCoとNISAの違い
- DC(確定拠出年金制度)とiDeCoの違い
iDeCoとNISAの違い
NISAはいつでも引き出し可能なのに対し、 iDeCoは60歳まで引き出すことができません。 60歳より前にお金を引き出したい、定期預金のように自由に引き出したいという人にとってiDeCoは向いていません。
一方、iDeCoは所得控除になって節税ができることがNISAにはない大きなメリットです。NISAのほうが自由度が高く投資をすることができますが、iDeCoは毎年節税をしながら老後の資産を安定的に増やしていくことができます。
iDeCoとNISAの詳しい違いは以下の表を参考にしてください。
DC(確定拠出年金制度)とiDeCoの違い
会社員の場合、iDeCoと似た制度としてDC(確定拠出年金制度)があります。DCは企業が掛金を払い、運用し、60歳以降に受け取れます。掛金も運用益も非課税になり、受け取る際の税制優遇措置もあります。
iDeCoと似ていますが、一番の違いは、 DCは企業が用意すること、iDeCoは自分で加入すること です。つまり、会社がDCを用意していなければ、DCには加入できませんし、逆に自分でも知らないうちに加入していたという場合もあります。
DCとiDeCo、同時に加入することもできますが、企業年金が手厚くて、その掛金が月55,000円以上だった場合、iDeCoには加入できません。
iDeCoが向いている人・向いていない人
最後にiDeCoが向いている人と向いていない人がどんな人か解説します。
この目次でわかること
- iDeCoが向いている人
- iDeCoが向いていない人
iDeCoが向いている人
iDeCoは 長期的に老後資産を形成したい人に向いています。 60歳まで引き出せないというデメリットも、自分で取り崩してしまう誘惑がないことがメリットだともいえます。
また、これまでも書いてきたように、iDeCoの最大のメリットは節税になることです。iDeCoには手数料がかかりますが、節税額が手数料を上回る場合がほとんどなので、手数料のデメリットよりも節税のメリットが上回ります。
自営業者・会社員ともに、老後資産を用意しつつ、今現在の税金の節税もしたいという人 にはiDeCoがピッタリです。
iDeCoが向いていない人
60歳より前に資金が必要になる可能性がある人には、iDeCoは向いていないといえます。 たとえば失業などをしてお金が必要になったとしても、原則としてiDeCoのお金は引き出せません。貯金をまったくせずにiDeCoにお金を回したり、日々の生活が苦しくなるほどiDeCoにお金を回すのはオススメできません。
また、 短期間で資産を増やしたい人、大きく資産を増やしたい人にとっては、iDeCoは最善の選択ではない場合が多い です。
まとめ 長期的な老後資産の形成にはiDeCoが◎
iDeCoには「デメリットしかない」と言い切るのは早計です。60歳まで引き出せないデメリットはありますが、手数料以上の節税効果や運用益の非課税メリットは大きな魅力です。iDeCoのメリット・デメリットをしっかり把握したうえで、自分にとって最適な資産形成の方法を選びましょう。NISAなどの他の選択肢と組み合わせることで、より柔軟な資産運用も可能になります。
将来のために今から正しいお金の知識を身につけ、資産形成を始めてみませんか?
資産形成には、情報収集と正しい知識が必要不可欠 です。今から始められる資産運用方法を専門家が無料でご提案します。一歩踏み出すことで、将来の不安を少しずつ減らすことができます。まずは無料相談で、あなたの資産形成プランを一緒に考えてみませんか?